初めての離乳食づくりで戸惑ったこと
赤ちゃんが生後5〜6ヶ月頃になると、いよいよ離乳食スタート。私も娘の離乳食を始めたとき、想像以上に大変さに驚きました。最初は「どうやって作ればいいの?」「どのくらい食べるの?」と不安ばかりで、レシピを見ながら作っても失敗の連続でした。
よくあった失敗その1:食べてくれない
初日のニンジンペーストは見事に拒否されました。泣きながら口を閉じる娘を見て、つい「何で食べないの?」と焦ってしまったことも。赤ちゃんには味覚が敏感で、初めての味や舌触りに慣れるまで時間がかかることを実感しました。
よくあった失敗その2:硬さが合わない
レシピ通りに作ったつもりでも、スプーンで掬ったときに「固い」と感じることが多々ありました。ペースト状にしたつもりでも、赤ちゃんの飲み込みやすさに合わせないとむせてしまうことがあります。
よくあった失敗その3:食材の選び方
離乳初期に避けたほうがよい食材やアレルギー注意食材をうっかり選んでしまったこともありました。初めての食材は1種類ずつ少量から試すことが大切だと痛感しました。
失敗から学んだこと
これらの経験から、「完璧を目指さない」「少しずつ試す」「赤ちゃんの反応をよく観察する」という基本を大事にするようになりました。失敗は避けられないけれど、そこから学ぶことが多いのが離乳食の面白いところです。
うまくいった工夫その1:調理家電を活用する
私が離乳食作りで最初に助けられたのは、ブレンダーや離乳食用スチーマーなどの調理家電です。特に、離乳初期のペースト作りは手作業だと時間もかかり、手も疲れます。
例えばスチーム機能付きのブレンダーを使うと、食材を蒸す時間とすりつぶす工程が一度で完了。ニンジンやカボチャも滑らかに仕上がるので、赤ちゃんが食べやすくなりました。
詳細はこちらの調理家電リンクを参考にしています。
ポイント:まとめて作って冷凍保存
一度に作る量を多めにして、製氷皿で小分けにして冷凍保存するのも便利です。解凍するだけで食事の準備ができるので、忙しい朝や夜もスムーズに対応できます。
うまくいった工夫その2:レシピサイトを活用する
初めての食材や味付けに迷ったとき、レシピサイトが強い味方になりました。食材ごとに段階別レシピが掲載されているので、「初期」「中期」「後期」と分けて参考にできるのが便利です。
私は特にこの離乳食レシピサイトをよく利用していました。
ポイント:赤ちゃんの反応を見ながら調整
どんなにレシピ通りに作っても、赤ちゃんによって好みや食べやすさは異なります。最初は小さく薄めに作り、徐々に濃さや硬さを調整するのがコツです。これを意識するだけで、食べてくれる率が格段に上がりました。
うまくいった工夫その3:手作り食材と市販品を組み合わせる
離乳食作りは毎日続くので、最初から手作りだけにこだわると疲れてしまいます。そこで私は、手作り食材と市販の裏ごし済み食材やベビーフードを上手に組み合わせるようにしました。
例えば、野菜はブレンダーで手作りし、たんぱく質は市販の無添加ペーストを活用。これにより、栄養バランスを保ちながらも調理時間を短縮できます。市販品も安心して使えるものが増えているので、うまく活用することが離乳食継続のポイントです。
ポイント:疲れた日は市販品に頼る勇気を持つ
「手作りでないとダメ」と思い込む必要はありません。忙しい日や体調が優れない日は、市販品に頼ることでママの負担を軽減できます。大切なのは、赤ちゃんとママが無理なく食事時間を楽しめることです。
まとめ|離乳食作りは完璧でなくて大丈夫
初めての離乳食作りでは、失敗や戸惑いがつきものです。私も最初は、食べない、硬さが合わない、食材選びで悩むことばかりでした。しかし、調理家電の活用、レシピサイトの参考、手作りと市販品の組み合わせなど、少しずつ工夫することで、無理なく続けられるようになりました。
ポイント:赤ちゃんの反応を優先する
レシピ通りに作れなくても、赤ちゃんが食べやすいかどうかが一番大事です。泣かずに食べられた日は小さな成功体験。嫌がった日も次回の調整につなげられます。
ポイント:ママ自身も楽しむ
離乳食作りはママにとっても育児の一部。自分が楽しめる工夫や、便利な道具を取り入れることで、気持ちの負担を減らすことができます。少しずつ慣れていけば、赤ちゃんとの食事時間も笑顔で過ごせます。
最後に|無理せず、楽しむ気持ちを大切に
離乳食作りは正解がないからこそ、失敗しても大丈夫。今日できなかったことも、明日につなげればOKです。赤ちゃんと一緒に少しずつ成長していく楽しさを味わいながら、無理せず、笑顔で取り組むことが一番大切です。
この記事で紹介した工夫を参考に、あなたも赤ちゃんとの食事時間を少しでもラクに、楽しく過ごせますように。
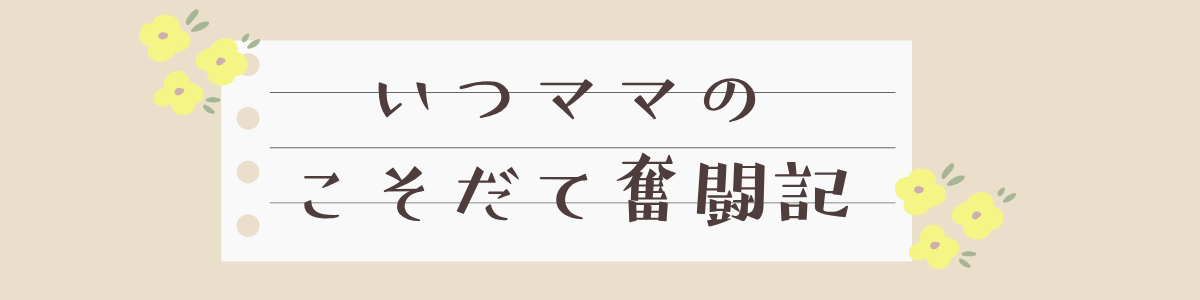

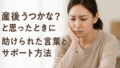

コメント