「1人時間がなさすぎる…」の限界からスタートした話
育児が始まってから、私が一番しんどかったのは “自分の時間がないこと” でした。家事・育児・寝かしつけで一日が終わり、自分に使える時間はゼロ。コーヒーを飲む5分すら確保できない日もありました。
この状態が続くと、疲れは積み重なり、気持ちにも余裕がなくなっていきます。ある日「このままじゃダメだ」と気づいた私は、時間をつくるために“やることを増やす”のではなく、“やめる習慣をつくる”方向に切り替えました。
結果的に、家事の負担は軽くなり、気持ちもラクになり、少しずつ1人時間を確保できるように。この記事では、私が本当にやめてよかった習慣を3つ紹介します。
1人時間をつくるには「足す」より「引く」ほうが現実的だった
スケジュール帳に「自分時間を作る」と書いても、現実はうまくいきませんでした。育児は予想外の連続だからこそ、余白をつくるために “やめる習慣” が効果的でした。
完璧主義を手放すと一気に楽になった
すべてを完璧にしようとするほど、時間はなくなる。子どもがいる生活では“7割で十分”と思えるだけで気持ちが軽くなりました。
1人時間を確保するためにやめた習慣3つ
① 毎日全部の家事をやろうとすること
私は“家事は毎日やるもの”という思い込みが強く、洗濯・掃除・料理を全部こなそうとしていました。でも実際は、毎日全部やる必要なんてありません。
例えば、洗濯は2日に1回に変更、掃除機はロボット掃除機に任せ、料理は宅食や冷凍食品を活用。こうした“家事の優先順位を下げる”ことで、一気に自由時間が増えました。
ロボット掃除機やドラム式洗濯乾燥機などの時短家電は、まさに救世主。長期的に見て「もっと早く導入すればよかった…」と思うレベルでした。
② 子どもが寝た後にまとめて家事をしようとすること
寝かしつけ後の時間を「家事タイム」にしていた頃、1人時間は全く生まれませんでした。疲れた夜に掃除や片付けを始めると、余計にストレスが溜まります。
そこで私は、夜の家事は最低限にして、翌朝のエネルギーがある時間にまわすことに。例えば、食器は夜に全部洗わず、朝の元気なタイミングでさっと片付ける。これだけでも夜に余白が生まれました。
「夜は自分のための時間」と決めることで、心の切り替えができるようになったのも大きかったです。
③ 子どもが起きている間に完璧な家を保とうとすること
子どもが小さい間は、部屋が散らかるのは当然。それでも私は「床に何も置かない」「常に片付いている状態にしたい」と無理していました。
でも、その完璧を求めるほど、自分の時間が失われました。そこで私は「片付けは寝る前の5分だけ」「日中は散らかっていてOK」というルールに変更。
散らかる→片付ける→また散らかる…という終わりのないループから抜け出せて、気持ちの負担が一気に減りました。
1人時間を確保するために意識したこと
① 「やらない日」をつくる
週に1日は家事をしない日をつくりました。洗濯も掃除も料理も“今日はしない”と決めるだけで、心身の休息になります。
② 家事を“タスク”ではなく“選択”に変える
「やらなきゃ」ではなく「やるか・やらないかを選ぶ」。この意識に変わるだけで、家事のプレッシャーが激減しました。生活を回せれば100点です。
③ お金で時間を買う選択肢を持つ
宅配サービス、時短家電、食材キット…こうしたサービスに頼るのは甘えではなく“投資”。疲れて余裕がない日ほど、外に頼るメリットを強く感じました。
ママの心の余白は、家族みんなの余白になる
① ママの余裕は子どもの安心につながる
自分の時間が少しでも持てるようになると、心に余裕が生まれ、子どもに優しく接することができる瞬間が増えました。
② 「休むこと」に罪悪感を持たない
休む=怠けている、ではありません。休む=家族のためにエネルギーをためる、です。これは本当に大事な考え方でした。
まとめ:やめるだけで、1人時間はつくれる
時間をつくるには、努力よりも“やめること”のほうが効果的でした。完璧主義を手放し、家事を減らし、頼れるものには頼る。それだけで、不思議なくらい余白が生まれます。
つくさんも、まずは今日「ひとつだけやめる習慣」を試してみてね。きっと気持ちがふっと軽くなるはず。
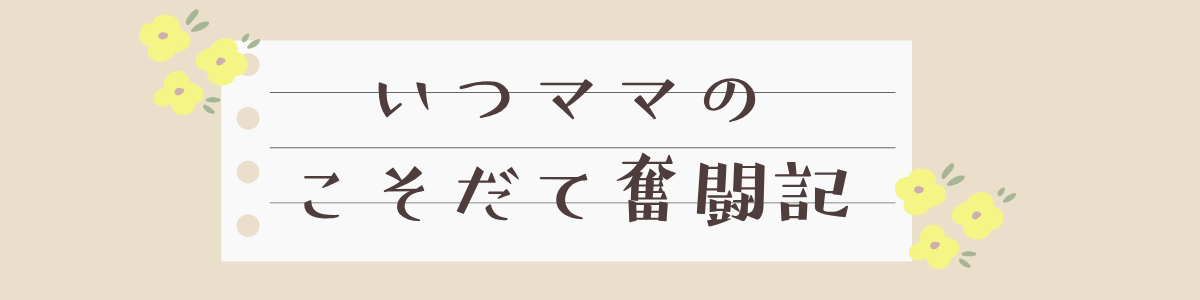
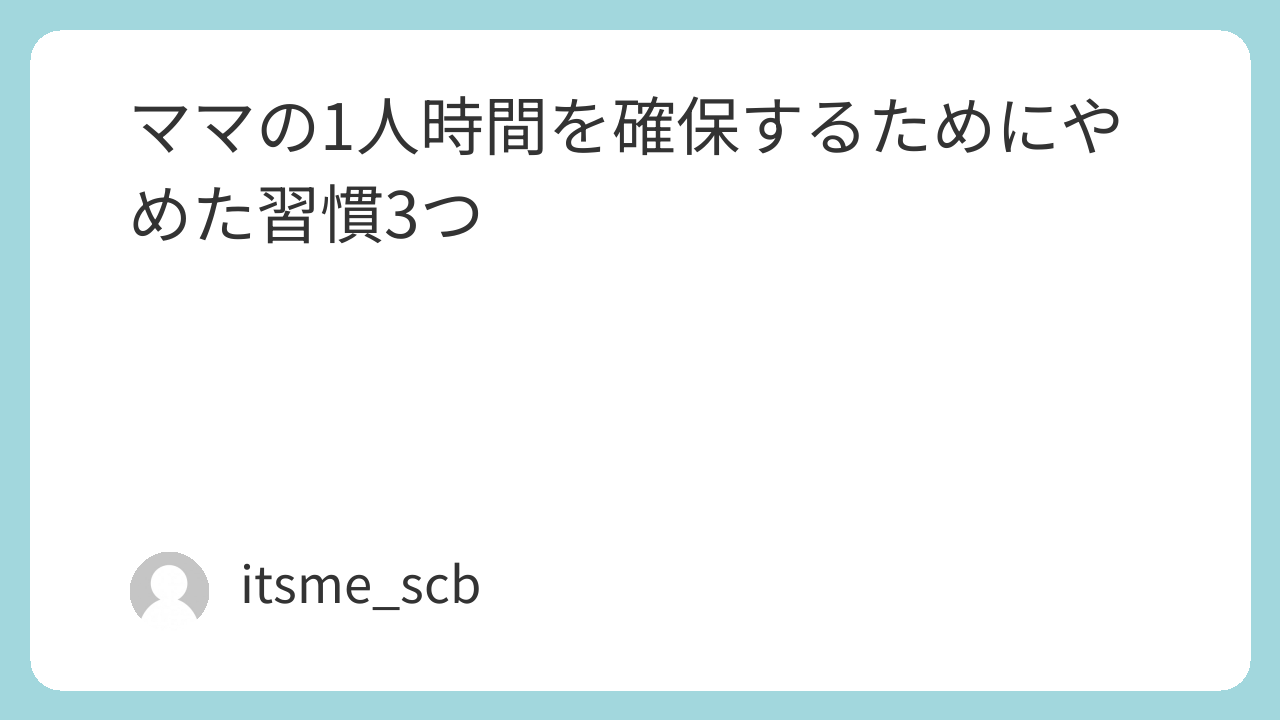
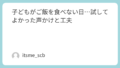
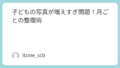
コメント