「仕事どうしよう…」から始まった病児保育利用の決断
子どもが急に発熱した朝、仕事の予定も詰まっていて、家族のサポートも難しい。そんな日に初めて利用したのが「病児保育」でした。それまで存在は知っていたものの、利用するのはなんとなくハードルが高い気がして、ずっと避けていました。
でも実際に利用してみると、スタッフの方がとても丁寧で、安心して預けられる環境が整っていました。「もっと早く知っていればよかった…!」と心から思えたほどです。
この記事では、私が初めて病児保育を利用したときの流れや準備、注意点をまとめています。これから利用するかもしれないママ・パパの参考になれば嬉しいです。
病児保育は“子どもが回復するまでの助け舟”
病児保育は、子どもが体調不良で保育園に行けない日に預かってくれる施設。発熱や咳、胃腸炎明けなど、「家では看たいけど仕事の都合が…」というときに頼れる存在でした。感染症の場合は預かり不可などの基準はありますが、思っていたより利用しやすい仕組みでした。
最初は不安が大きくても大丈夫
「病気の子を預けてもいいの?」「ちゃんと見てもらえる?」と心配だらけでした。でも実際は、医療知識を持つスタッフが細かくケアしてくれました。親の不安に寄り添ってくれる雰囲気があるので、初めてでも安心できました。
病児保育を利用した日の実際の流れ
① まずは当日の朝に電話予約
多くの施設は“当日予約制”。朝8時〜9時頃に電話で状況を伝え、空きがあれば利用できます。「熱は何度か」「食欲は」「水分はとれているか」など基本的な質問をされました。
② かかりつけ医の診断書が必要な場合も
施設によっては、利用前に小児科で診断書(利用連絡票)が必要なことがあります。私は一度小児科に寄り、「病児保育利用OK」と書いてもらってから施設へ向かいました。診察が必要な場合もあるので、少し早めの行動がおすすめです。
③ 施設に到着して書類の記入
到着すると、スタッフの方が丁寧に状態をヒアリングしてくれます。普段の様子や好きなおもちゃ、アレルギーなどを記入する用紙もありました。子どもは別室で遊びながら待てるため、安心して書くことができました。
④ 子どもを預けて仕事へ
最初は泣いてしまいましたが、スタッフの方が抱っこして落ち着かせてくれました。泣いても責められない雰囲気がありがたく、「任せてくださいね」と優しく言われて心がほどけました。
⑤ 日中の様子を細かく記録してくれる
食事、睡眠、水分補給、トイレなど、子どもの様子を細かく書いてくれます。お迎えのときに渡される記録がとても丁寧で、家に帰ってからのケアにも役立ちました。
⑥ お迎え後にスタッフからフィードバック
「食欲はこんな感じでした」「お昼寝はこれくらいできました」と、口頭で説明してくれました。小さな変化にも気づいてくれるので、家での対応がしやすかったです。
病児保育を使うときに知っておいてよかった注意点
① 予約は“早い者勝ち”の施設が多い
病児保育は定員が少ないため、特に冬場はすぐ埋まります。「行くかも…」と思った時点で電話して相談するとスムーズでした。
② 子どもの状態を正確に伝えることが大事
熱の変化、嘔吐・下痢の有無など、正確な情報のおかげでスタッフの方が適切にケアしてくれました。少しでも不安な点は全部伝える方が安心です。
③ 持ち物は少し多めに準備
おむつ、着替え、タオル、水分、薬、食事など、「想定より多め」に持たせると安心でした。特に汗をかきやすい子は着替えが多いと助かります。
④ 感染症は預けられない場合がある
インフルエンザや胃腸炎など、施設によって預かりNGの感染症があります。事前に自治体や施設の基準をチェックしておくと、慌てずにすみます。
⑤ 親のメンタルが軽くなると、家の雰囲気もよくなる
病気の子を見ながら仕事も…となると、精神的にかなりしんどい。病児保育を利用することで少し心に余裕ができ、「帰ったらいっぱい抱っこしよう」と優しい気持ちで迎えられました。
病児保育を使ってみて感じたこと
「親が無理しない」ためのサービスだった
利用前は“申し訳ない”気持ちがありましたが、実際は「親が無理をしないため」にあるサービスなんだと実感しました。仕事を休めない日や、看病が続いて心が限界の日に、とても支えになりました。
スタッフの丁寧さに救われた
病児保育のスタッフは、子どものケアだけでなく、親の不安に寄り添ってくれる存在でした。「今日はゆっくりお仕事してくださいね」と言ってもらえただけで涙が出そうに…。本当に安心材料になりました。
まとめ:病児保育は“頼っていい場所”
病児保育は決して特別なものではなく、必要な日に頼れる身近なサービス。利用してみると肩の力が抜け、家庭全体が救われる場面も多いです。
つくさんが「今日は無理かも…」と感じる日があったら、迷わず頼って大丈夫。支えてくれる仕組みは必ずあります。
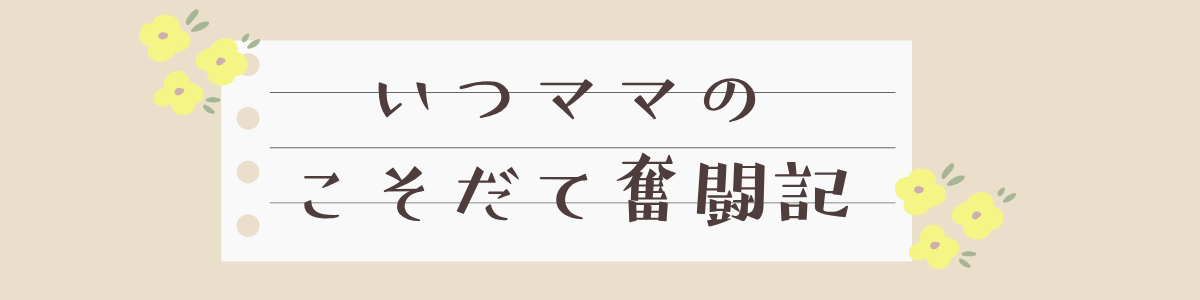

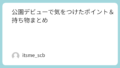
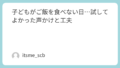
コメント