「食べない日」って必ずある。悩みすぎていた私の話
毎日の食事で一番悩んだのが、「子どもが全然食べない日」。大好きなメニューでも食べなかったり、口に運んでもすぐポイしたり…。私はそのたびに「作ったのに…」「栄養足りてる?」と不安とイライラが混ざってしまっていました。
でも、小児科の先生や栄養士さんに相談した時に言われたのが「子どもは食べる日と食べない日があって当たり前」という言葉。そこから少し気持ちが軽くなり、“全部食べさせる”よりも“食事時間を心地よくする”ほうに意識を向けるようになりました。
この記事では、我が家で実際に効果があった声かけや工夫をまとめています。今日食べなくても大丈夫だよ、という気持ちで読んでみてくださいね。
まずは「食べない=悪いことじゃない」と知る
食欲は大人でも日によって違うもの。子どもならなおさら波があります。「今日はあまり食べない日なんだな」と思えるようになるだけで心がラクになりました。
親が焦ると、子どもにも伝わる
「早く食べて」「なんで食べないの?」という気配を出すと、子どもは敏感に感じ取ってしまいます。私も焦りが伝わって余計に悪循環になったことが…。雰囲気は本当に大事でした。
ご飯を食べない日に試してよかった声かけ
① 「無理に食べなくていいよ」
最初のひと言で空気が変わります。安心すると、あとから食べてくれることも多かったです。否定ではなく、気持ちに寄り添う声かけから始めるようにしました。
② 「一口だけ食べてみる?」
“全部食べて”よりハードルが低いので、子どもも応じやすい声かけでした。無理な日は本当に一口で終わる日もありますが、それでもOKにしました。
③ 「どっちが食べたい?」と選択肢を用意
スプーンで食べる?手づかみ?など、選べるようにすると自主性が出て気分が変わることがありました。メニューではなく“食べ方”を選ばせるのも効果的でした。
④ 「ママも食べてみようかな〜」と見せる
一緒に食べる姿を見せると、子どもは“真似したいスイッチ”が入ることがありました。美味しそうに食べる姿を見せるだけで反応が変わる日もありました。
⑤ 「食べられたら嬉しいけど、食べられなくても大丈夫」
プレッシャーを取り除いてあげる声かけ。安心すると、スプーンを持とうとしてくれる日が増えました。
食べない日に役立った工夫5つ
① 食べる量を“目で見て分かるくらい少なめ”にする
最初から量が多いと拒否されることが多かったので、最初はひと口サイズだけ盛るようにしました。成功体験が積みやすく、子どもも「食べられた!」と達成感を感じているようでした。
② いつものお皿を変える
ワンプレートや仕切り付きのお皿、好きなキャラのお皿などを使うと気分が変わることがありました。視覚で楽しめる工夫は結構効果的でした。
③ 手づかみ食べできるメニューを混ぜる
スプーンが嫌な日は、とにかく手でつかめるものが救世主。おにぎり、蒸し野菜、バナナなど、簡単につまめるメニューは食べてくれる確率が高かったです。
④ 椅子の高さ・足置きを調整する
椅子が合っていないと食べづらく、落ち着きにくいことがあります。足がしっかりつくように調整するだけで、食事に集中しやすくなりました。
⑤ 食べない日は“完食させない勇気”を持つ
食べない日に無理をさせると逆効果だったので、「今日はこれで終わり」と切り上げる勇気も大事でした。次の食事で自然と食べてくれることも多かったです。
親の心が軽くなる考え方
① 3日〜1週間で食べる量を見ればOK
1食単位で一喜一憂すると本当に疲れます。栄養士さんにも「1週間トータルで見てね」と言われ、気持ちがぐっとラクになりました。
② 子どもは“必ず食べる日”がやってくる
不思議と、数日後にはモリモリ食べる日が訪れます。波があるからこそ、食べない日があっても心配しすぎなくて大丈夫でした。
③ 楽しい雰囲気が“食べたい気持ち”につながる
食事は量より雰囲気が大事だと思うようになりました。笑いながら食べたり、会話を楽しんだりすると、自然と食べてくれる日が増えました。
まとめ:食べない日があっても大丈夫
子どもの食事は思い通りにならない日があって当然。食べない日は責めるのではなく、「そういう日なんだな」と受け止めることで心がラクになります。
今日食べなくても、明日食べる日が来る。その繰り返しで大丈夫。つくさんのペースを大切に、無理せず続けていきましょう。
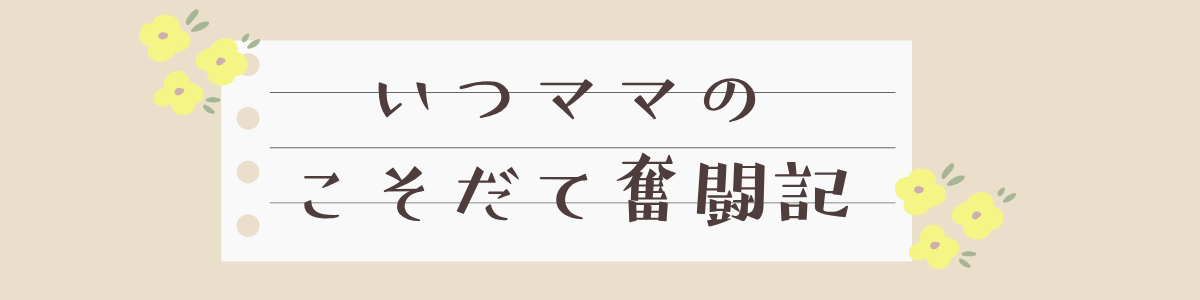
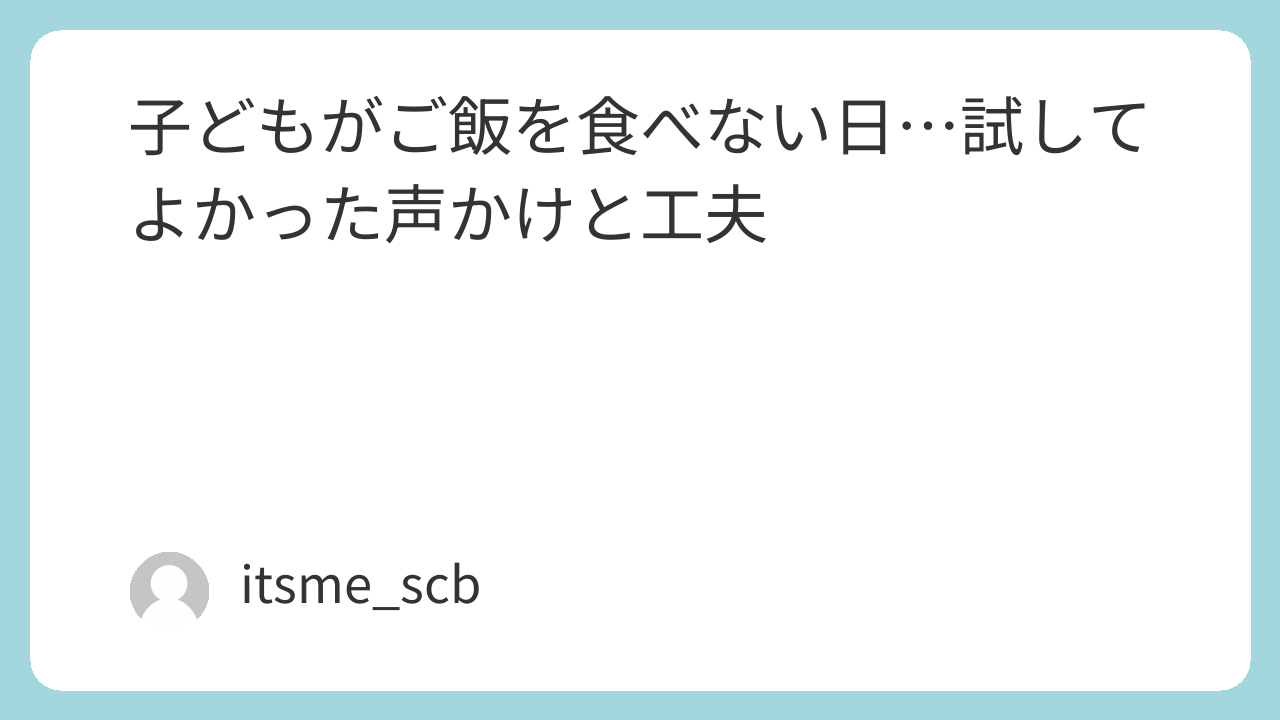

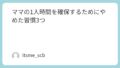
コメント